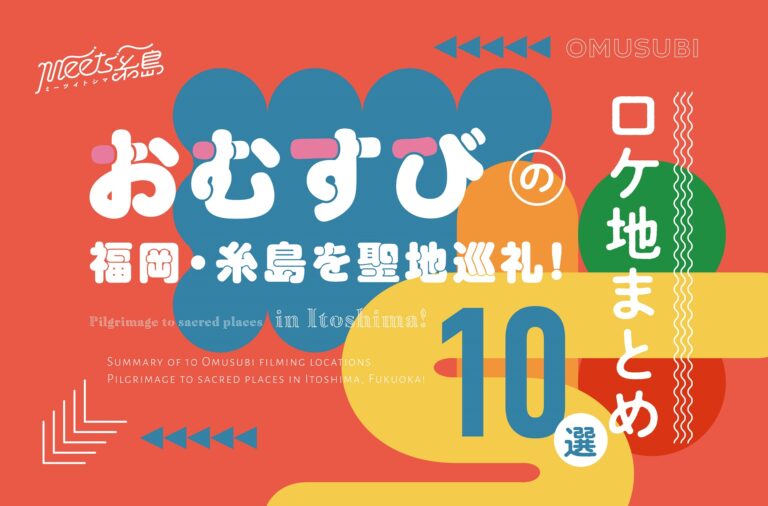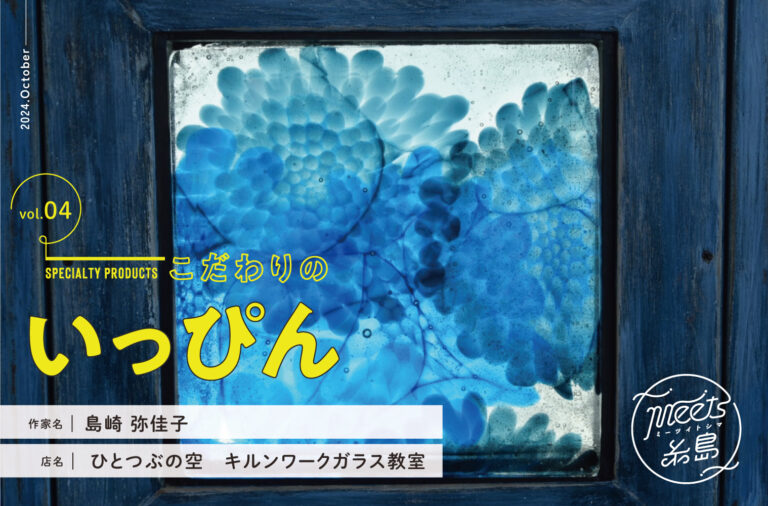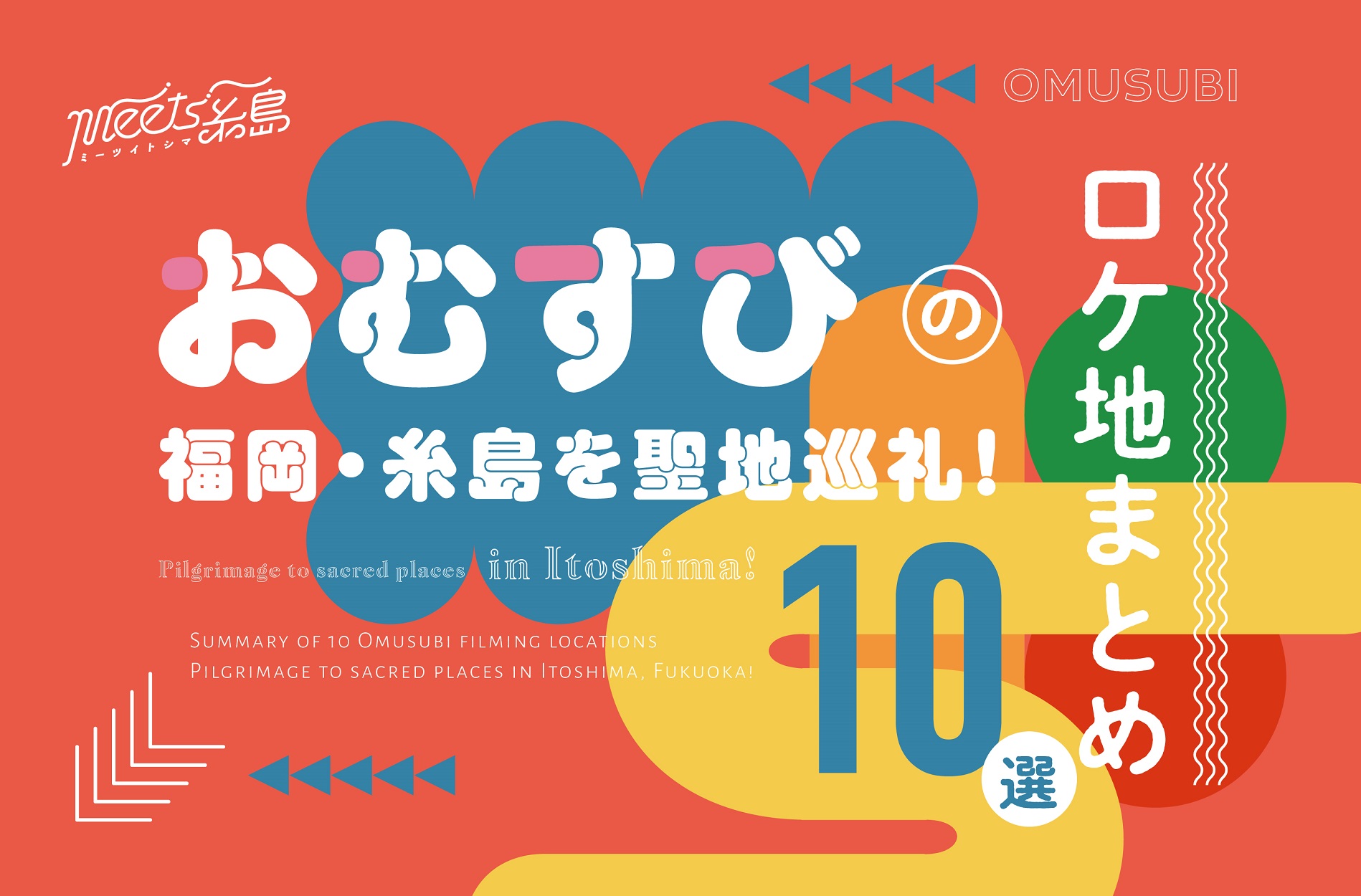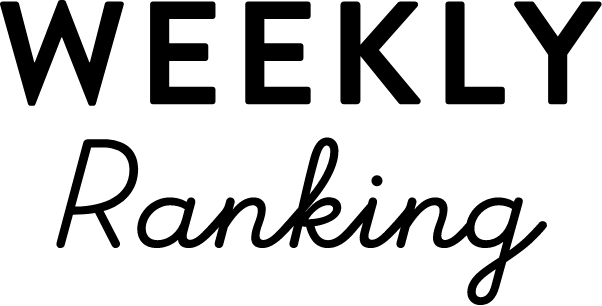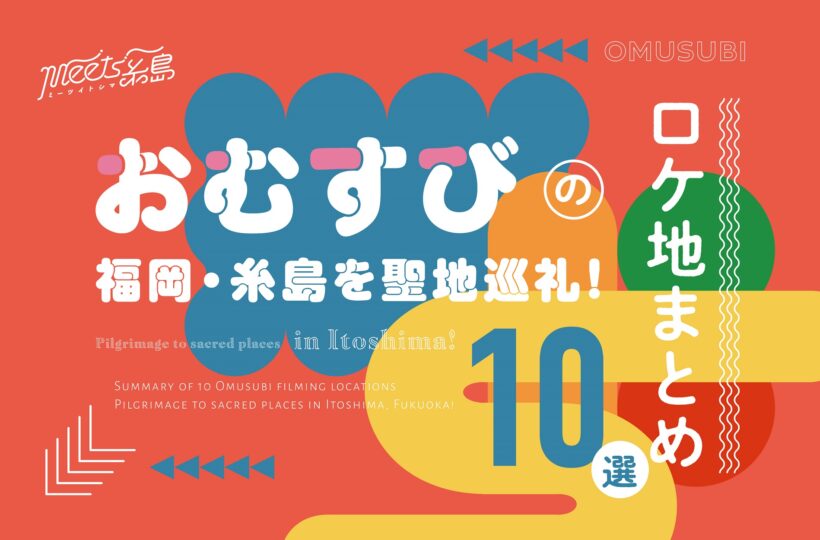やきもの好きにはたまらない、芥屋にある糸島唯一の登り窯「唐津焼 高麗窯」を探訪!<③技法編>
みなさんはやきものと聞いて、何を思い浮かべますか?
伊万里焼、有田焼、波佐見焼など、イメージするやきものは人それぞれでしょう。
筆者は今回、芥屋にある糸島唯一の登り窯「唐津焼 高麗窯」さんを探訪。
そこには、筆者にとって新鮮な驚きと発見が数多くありました。
目次
古唐津に興味を抱き、クリーニング屋から窯元へ。見ているだけで楽しくなる、多種多様なやきものが並ぶ「唐津焼 高麗窯」
こちらの記事は、『やきもの好きにはたまらない、芥屋にある糸島唯一の登り窯「唐津焼 高麗窯」を探訪!<②様々なやきもの編>』の続きになります。
今回は、絵唐津や焼き締め、粉引などの技法を使った作品に注目してご紹介していきます!
絵唐津
絵唐津は、器に鉄絵の具で素朴な文様を描いたものです。
●絵唐津

朝鮮唐津
斑釉(まだらゆう)と飴釉(あめゆう)の2種類の釉薬をかけたものの総称を朝鮮唐津といいます。
その中でも、釉薬が溶けて混ざり合った部分が青っぽく発色したものがナマコ、ピンクっぽく発色したものが辰砂(しんしゃ)です。
こちらの写真が、器の表側(火に対して表側)になります。ナマコと辰砂の両方の変化がよく出ています。

そしてこちらが、器の裏側(火に対して裏側)。

2枚の写真はどちらも同じ器のものですが、表面と裏面で模様が大きく異なっています。まるで「動」と「静」を象徴している感じがあって、筆者は好きです。
焼き締め
焼き締めは、鉄分の多い土から作られています。
備前唐津や南蛮唐津とも呼ばれており、重厚感のある器です。
他の陶器と大きく違うのは釉薬(ゆうやく)をかけていないところで、窯の中でかぶった灰が天然の釉薬となり、深い味わいとなるそうです。
●焼き締め

写真にあるような湯呑だけではなく、壺や一輪差しなど焼き締めという技法が使われている器はいっぱいありました。
灰かぶり
一般的な「灰かぶり」とは違って、まるで自然に灰がかぶったような、高麗窯さん独自の技法のひとつです。
●灰かぶり鉢

同じ灰かぶり鉢でも1つひとつ模様が若干異なっていて、面白いですね。
あなたなら、どの器を選びますか?
粉引
●粉引

粉引(こびき)とは、白い化粧土を使ったやきもの。
握りしめたくなるような、温かみのあるやわらかな白色が特徴的です。
●粉引湯のみ

粉引の湯のみもありました。緑茶や紅茶が似合いそうな器ですね。
筆者がいま家で使っているお茶碗と見た目が似ているので、もしかしたら筆者のお茶碗にも粉引という技法が使われているのかもしれません。
刷け目
こちらの刷け目(はけめ)という技法もまた、粉引と同じように白い化粧土を使います。
●刷け目

粉引が白い化粧土で器全体を包むのに対して、刷け目は刷毛(はけ)を使って器を部分的に白く装飾します。
刷毛の種類や、刷け目の動かし方によって模様が変わる面白さがあるとのこと。
個人的には、下の写真の左手前にあるような、ぐるぐると渦を巻いた模様の器が好きです!
じっと見つめていると、どこか違う世界に引き込まれてしまいそうです。
古き良きものを再利用
実は高麗窯さんでは、お店の柱に、昔使われていた木製の電柱を使っているそうです。
「え、これですか?」木製の電柱を見たことがない筆者は混乱し、別の柱を指さして尋ねてしまいました。
「違う違う、こっちだよ」
導かれるままに壁の方を見ると、なるほど年季の入った柱がそこにあります。
すぐ下に並んでいる器や壁面の色合いとよく合っているので、最初はどの柱なのか見つけられないほどでした。

いまどき、昔使われていた電柱を使っているお店も珍しいですね!
今も問題なく使えているようなので、よほど作りがしっかりしているのでしょう。
筆者が昔電柱だった柱を見て感慨にふけっていると、高麗窯の古家さんはさらに「天井を見てごらん。これは糸島にある桜野小学校の校舎に使われていた合掌だよ」と教えてくれました。

ちなみに桜野小学校は、糸島の桜井・野北地区の子どもたちが通う小学校だそうです。
校舎をコンクリートに建て替えるときに、解体業者の方にお願いして譲ってもらったのだそう。
こちらも落ち着いた色合いで、味があって良いですね~!
次回はいよいよ窯見学!
ここまで絵唐津、朝鮮唐津、焼き締め、灰かぶり、粉引、刷け目といった技法を使った器についてご紹介してきました。
最後の方では、昔の電柱や校舎の一部など古き良きものたちについてもお話ししましたが、いかがだったでしょうか。
高麗窯さんは、知れば知るほど面白い部分や魅力的な部分が出てくる、とっても素敵なお店です!
さて、次回はいよいよ高麗窯さんの命ともいえる「登り窯」を見学します。
お楽しみに!
続きは以下のリンクからご覧いただけます。
『やきもの好きにはたまらない、芥屋にある糸島唯一の登り窯「唐津焼 高麗窯」を探訪!<④窯見学編>』
INFORMATION
店名:
唐津焼 高麗窯
住所:
福岡県糸島市志摩芥屋157
電話番号:
092-328-2353
営業時間:
10:00〜17:00
定休日:
火・水曜日
一人当たりの予算:
¥1,000~
※記事内の情報は記事執筆時点のものです。正確な情報とは異なる可能性がございますので、最新の情報は直接店舗にお問い合わせください。